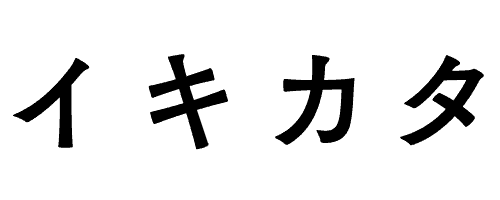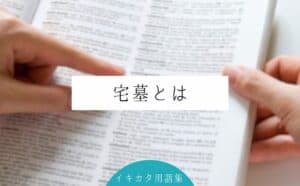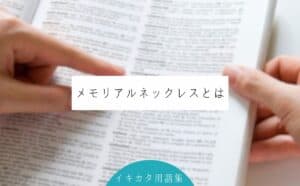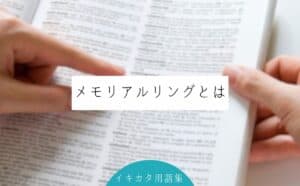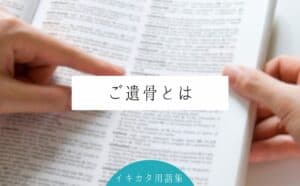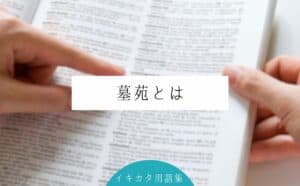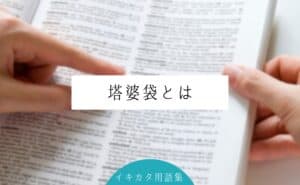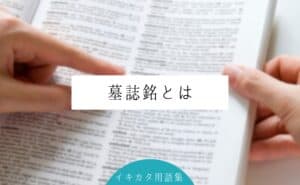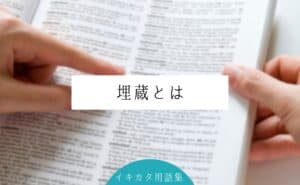本ページはプロモーションが含まれています。
のし紙とは?|意味や種類・表書きの書き方やマナーを解説
のし紙とは贈答品の表にかける紙のこと
のし紙とは、贈答品にかける白地の紙です。基本的にのし紙とは「のし」と「水引」がついている慶事用のものですが、現在は弔事用のものも「弔事用のし」として扱われることが多く、こちらは「掛け紙」とも呼ばれます。ここではのし紙の意味や歴史をはじめとして、のし紙の種類や表書きの書き方、使い方のマナーについても解説します。
のし紙の意味や歴史をチェック
のし紙や掛け紙は、贈り物に気持ちを込め、目的をあらわすための贈答のマナーです。のし紙は、白地の長方形の紙で、中央には水引が印刷され、慶事用には右上にのしが付いています。のし紙の歴史は古く、細かいしきたりがあるので、相手への敬意をあらわすためにも、正しい使い方を身につけましょう。
のしは熨斗鮑(のしあわび)に由来
のし紙の”のし”は、熨斗鮑(のしあわび)に由来します。熨斗鮑とは、乾燥させた鮑のことで、2000年以上に渡り伊勢神宮に奉納される、最上級の供物(くもつ)の一つです。味の良さ、栄養価の高さはもちろん、製造時の「伸す(のす)」工程が、長寿の祈念につながるとして、古くから珍重されてきました。江戸時代になると、熨斗鮑の束を紙に包んで水引をかけたものを贈答品に付ける習慣が定着し、これが現代の、のしの原型になったと言われています。のしの中心に挟む黄色の短冊は、鮑の象徴として添えられているものです。
のしは、生ものを添えたことを表しているので、生もの以外の贈答品に付けるのがマナー。つまり鮮魚や精肉、かつお節などの生ものを贈る場合は、のしは必要ありません。また、生ものがタブーとされる仏事のお供えには、のしは不要です。
のし紙は英語で『gift wrapping paper』
のし紙は英語に訳すと『gift wrapping paper』または『wrapping paper』となります。そもそも外国には、のし紙の習慣がなく、”のし”に相当する英単語も存在しません。そのため外国でのし紙の説明をする状況になる可能性は低いでしょう。
ここでは、外国人にのし紙を使うかをたずねる際の参考として、例文を紹介します。
例文1:のし紙をおかけしましょうか?
Could I attach a Japanese gift wrapping paper to the gift?
例文2:のし紙はのし付きにいたしますか?
Would you like to attach a decoration of folded red and white paper on the wrapping paper?
のし紙の種類と選び方
のし紙には慶事用と、弔事用(掛け紙)があります。間違った使い方をすると、相手に失礼になるので、正しい知識を身につけましょう。ここでは、のし紙の選び方や水引の色や本数、結び方の違いについて解説します。
のし紙と掛け紙の違い
結婚式や出産祝いのようなお祝いの贈答品には、のし付きののし紙を使います。のし紙の右上に紅白ののし飾りがついているのが特徴です。水引が印刷されている場合は、お祝いごとにふさわしい紅白や金銀のような華やかな水引の色を選びましょう。
一方、香典返しのようなお悔やみの贈答品には、のしが付かない掛け紙を使います。掛け紙の水引の色は白黒もしくは黒銀が多く、仏教のシンボルとして蓮の花が印刷してあるタイプも。
水引の色と種類
水引はのし紙に印刷されている場合が多いので、改めて水引を用意することは、現代ではほとんどありません。しかし水引の種類や結び方、本数の意味を知ることは、贈答のマナーを身につけるうえでも大切です。特に色や結び方は、使い方を間違えると相手に不快感を与える可能性があるので気を付けましょう。
水引の色
慶事用と弔事用で、使う水引の色とふさわしい贈答品の種類を紹介します。
『慶事に使う色』
| 水引の色 | 贈答品の種類 |
| 紅白 | 慶事の贈答品全般 |
| 金銀 | 結婚式や長寿の祝いなど、一度きりの祝いの品 |
『弔事に使う色』
| 水引の色 | 贈答品の種類 |
| 黒白・黒銀 | 弔事の贈答品全般 |
| 黄白 | 関西や北陸地方で弔事の贈答品 |
| 双銀(そうぎん) | 女性が香典を出す際やキリスト教の弔事の贈答品 |
| 双白(そうはく) | 神式で行う弔事の贈答品 |
水引の結び方と意味
結び方の意味やふさわしい贈答品の種類を紹介します。
| 結び方 | 結び目の特徴・意味 | 贈答品の種類 |
| 蝶結び | 結び目が蝶のような形に見える結び方です。「何度も結び直せる」の意味から、何度くりかえしても良い贈答品に使います。 | 出産祝、入学祝、お歳暮、お中元など |
| 結び切り | 結び目が堅結びにしてあり、先端が上に左右で開くような形になる結び方です。中心が解けないように固く結ぶことで、「同じことが起こらないように」と祈念する意味があります。 | 結婚祝、病気見舞い、快気祝、弔事の贈答品全般 |
| あわじ結び | 結び目が両サイドで輪になり、まるで無限(∞)のような形になる結び方です。結び切りよりもさらに複雑で解けにくいことから、「末永く続くこと」を祈念する意味と「今回かぎり」の意味で使われます。 | 結婚祝、弔事の贈答品 |
| 梅結び | 結び目が梅の花のような華やかな結び方です。結び目が複雑で解けにくいうえに、梅の花に運命が上向くという意味があり、さらに松竹梅の縁起の良い花でもあることから、「簡単には解けない」という祈願が込められています。 | 結婚祝 |
水引の本数
水引の本数は、慶事と弔事で適した本数が異なります。慶事では奇数本を、弔事では偶数本を使うのが原則です。例外として、結婚式では10本の水引を使うこともあります。
慶事では、5本の水引がもっとも一般的です。さらに丁寧なのが7本。親しい人への祝いとして、よりしっかり気持ちを込めたいときは7本が良いでしょう。また、慶事では水引の数は奇数が原則ですが、結婚式では新郎新婦両家が縁を結んだという意味で、5本の2倍で10本の水引を使う場合もあります。
弔事では、4本の水引が基本です。関係が深い人やお世話になった人に対しては、より気持ちを込めて6本にしても良いでしょう。簡易に済ませたい場合は、水引を2本にする場合もあります。
また、9本は「苦」を連想させることから慶事、弔事ともに使うのはNGです。
のし紙の表書きの書き方
のし紙や掛け紙の表書きには、さまざまな種類があります。表書きの目的は、どんな意味の贈り物なのかを相手に伝えることです。表書きを間違えると、受け取った相手を困惑させてしまう可能性があるため注意しましょう。
表書きの種類
表書きの種類は、慶事と弔事の場合と、その他の場合で次のようなものがあります。
慶事の表書き
| 表書き | 目的 |
| 寿 | 結婚式に参列した人への引出物 |
| 結婚御祝 | 結婚する新郎新婦への祝いの品 |
| 出産御祝 | 出産した家への祝いの品 |
| 出産内祝 | 出産祝いをいただいた人へのお返しの品 |
| 快気祝 | 病気から回復した人への祝いの品 |
| 御祝 | 入学祝、新築祝など祝い事全般に贈る祝いの品 |
| 内祝 | 祝いの贈り物をいただいた人へのお返しの品 |
弔事の表書き
| 表書き | 目的 |
| 会葬御礼 | 葬儀の参列者へのお礼の品 |
| 志 | 香典返し(東日本中心) |
| 偲び草 | 神道やキリスト教の香典返し |
| 粗供養(そくよう)満中陰志(まんちゅういんし) | 香典返し(西日本中心) |
その他の贈答品の表書き
| 表書き | 目的 |
| 御中元・御歳暮 | お中元・お歳暮の贈答品 |
| 粗品 | 感謝をあらわす贈答品 |
| 御挨拶 | 引越しなどの挨拶の贈答品 |
名前を書く位置
名前の位置は、水引を境にして下段の中央に縦書きで入れます。個人で贈る際にはフルネームを、家族で贈る際は「〇〇家」、連名で贈る際は左から優先度の高い人を順に書き入れましょう。
表書きを書く際のマナー
表書きは毛筆で書くのが正式です。慶事や通常の贈答品には濃墨(こずみ)を使いますが、弔事では贈る時期によって濃墨と薄墨を使い分ける必要があります。
仏教では四十九日を区切りに忌明け(きあけ)とされているので、四十九日より前には悲しみをあらわす薄墨を、それ以降は忌明けとなるので濃墨を使いましょう。
のし紙の掛け方
のし紙や掛け紙のかけ方には、内のしと外のしがあり、贈答品の種類や贈り方によって使い分けることが大切です。
内のしとは
内のしとは、のし紙や掛け紙をかけた上から包装紙で包む方法です。表書きをあえて隠すことで、つつしみの気持ちをあらわします。
内のしが適しているのは、内祝いのように家であった祝い事に使う贈答品です。個人的な幸せなので、おすそ分けするときは「つつしみをもって贈る」という意味で、内のしが品があるとされています。
また郵送で贈る際は贈答品が傷つかないように、内のしにするのがベターです。
外のしとは
外のしとは、贈答品を包装紙で包んだ上からのし紙や掛け紙をかける方法です。内のしとは逆に、表書きをはっきり示したい時に適しています。
結婚祝や出産祝など、第三者を祝福するための贈り物には外のしがベスト。また香典返しを直接渡すときも、感謝の気持ちを示すという意味で外のしにしましょう。
まとめ:のし紙はかしこまった贈答品には欠かせない合理的なマナー
のし紙の習慣を堅苦しく感じる人もいるかもしれませんが、実は、贈り物に気持ちを込めて、さらに目的をわかりやすく表現できる合理的なアイテムでもあるのです。のし紙の歴史や意味を知ることは、のし紙の価値を再認識することにもつながります。
1)KASHIYAMA(カシマヤ)
KASHIMAYA(カシマヤ)は、高品質ながら手頃な価格で、自社工場で最新技術を駆使したオーダースーツを最短1週間での納期を実現しました。また、2021年3月にスタートした新ライン「KASHIYAMA EASY」は、商品の品質や自動採寸の精度、納期、着こなしの汎用性に自信を持っています。これにより、より多くの人々が快適なオーダースーツを手に入れることができます。
KASHIMAYA(カシマヤ)のオススメデザイン
KASHIMAYA(カシマヤ)のセットアップスーツ/オーダーメイドスーツ

「身長・体重・年齢・体型」を入力するだけで、あなたにぴったりのサイズを提案するオンライン完結型のオーダーメイドシステム。採寸結果に基づいて1cm単位で調整が可能であり、日本人の90%以上の体型に対応する高い採寸精度を誇ります。
さらに、オーダーなのに最短1週間での納期を実現。超撥水性やウォッシャブル、超軽量、ストレッチなど、約150種類の素材やカラーを用意しています。オーダーメイドならではのデザインバリエーションもあり、ジャケットは2型、パンツは4型から選ぶことができます。これらの特長が、より快適なオーダーメイドスーツを実現しています。
《参考》KASHIMAYA(カシマヤ)
2)ORIHICA(オリヒカ)
ORIHICA(オリヒカ)は、メンズ&レディースのビジネスカジュアルブランドです。現代の多様な働き方に合わせて、ビジネスからカジュアルまで幅広い商品を取り揃えています。
ブランドのコンセプトは「新しいライフスタイルの鍵」。次世代のライフスタイルを切り拓く存在として、カテゴリーにとらわれずにアイテムを自由に編集する楽しさを提案しています。ORIHICAは、個々のスタイルやニーズに合わせたオシャレな選択肢を提供します。
ORIHICA(オリヒカ)のオススメデザイン
ナノブラック フォーマルスーツ 通年

社会人にとって必須のブラックフォーマル(喪服・礼服)は、特殊な加工を施した生地を使用しています。羊毛表面のスケールを取り除き、ナノレベルの染色剤を使って繊維の奥深くまで濃い黒を浸透させています。一般的なブラックスーツよりも上品で深みのある黒を実現しました。特に格式高い結婚式や披露宴では、濃い黒の方がよりフォーマルな印象を与えます。さらに、カーボン繊維を混紡することで、埃がつきにくくなっています。
このブラックフォーマルには、光沢感のあるピアノブラック釦が使用されています。光沢感がよりフォーマルな雰囲気を演出します。背中の裏地がなく背抜き仕様になっているため、オールシーズン着用可能です。さらに、ウエストアジャスターがあり、体型の変化にも対応しています。これにより、長く着用することができる魅力的なスーツです。着用頻度の低いスーツであるからこそ、これらの仕様は嬉しいものです。
《参考》ORIHICA(オリヒカ)
喪服・礼服・数珠をレンタルするという選択
喪服や礼服はいざという時に必要ですが、それ以外の時にはクローゼットの奥に眠っていることが多いですよね。また、必要になるのはいつも突然で、クリーニングに出す暇がない、なんてこともありませんか。
急な状況でも綺麗な喪服・礼服を準備するならレンタルという選択肢があります。
例えば「Cariru BLACK FORMAL」はドレスレンタルCariruが培った信頼と実績を、ブラックフォーマル特化させたフォーマル専門のレンタルサイト。質にこだわり、時代に合った高いデザイン性と確かなブランド力を提供しつつ、初めてブラックフォーマルを利用する方や、サイズやデザインに合わなくなった方、上質を求める方に向けて、Cariruが品質の高い選択肢を提供しています。
また、すべての商品は弔事のマナーに厳密に則って厳選されているため、突然の訃報に直面しても、通夜や葬式などへ参列できます。必要な時に必要なものがすべて揃う、デザイン・質・マナーを疎かにできない大人のためのブラックフォーマルレンタルがCariru BLACK FORMALです。