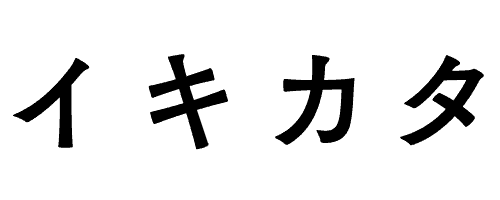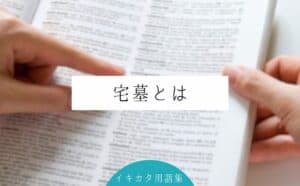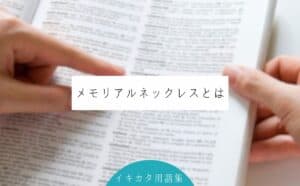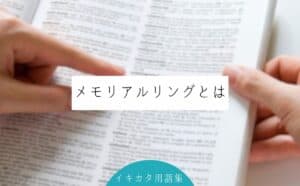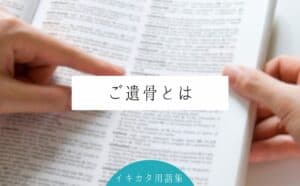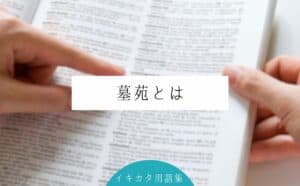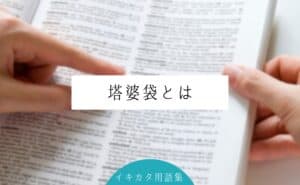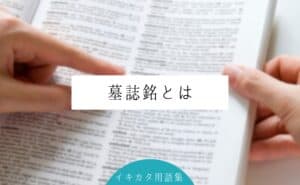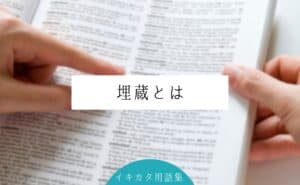本ページはプロモーションが含まれています。
御仏前とは?|御仏前の意味や使い方を解説します
御仏前は仏前の丁寧語で香典などの表書きに使う言葉
御仏前とは仏前を丁寧に言った言葉です。主に四十九日法要後の香典やお供え物の表書きとして記されます。また浄土真宗の場合は、お通夜や告別式の際にも「御仏前」を用います。同じ仏教であっても宗派により言葉の使い方が違うこともあるため、注意が必要です。この記事では、御仏前という言葉の意味や歴史、例題を用いて使い方を解説していきます。
御仏前の意味をチェック
御仏前(ごぶつぜん)とは、仏前を丁寧にいう言葉です。法事などで使用する香典袋やお供え物に添えるのしの表書きとして使用されます。
御仏前は英語で『before a Buddha or a mortuary tablet』
御仏前を英語に訳すと、『before a Buddha or a mortuary tablet』になります。
例文1:御仏前にお供えを用意する
I prepare for an offering in the Buddhist altar
例文2:御仏前を前に一礼する
I bow in front of a Buddhist altar
「御霊前」との違い
御仏前に似た言葉として「御霊前(ごれいぜん)」があります。たった一文字の違いであっても間違えてしまうと、大変失礼だと感じられることもあります。どんな違いがあるのか、しっかり把握しておきましょう。
どちらも香典袋の表書きだけれど…
御仏前は既にご紹介したとおり、香典袋などの表書きに用いられる言葉です。しかし、仏前を丁寧にいう言葉である御仏前に対し、御霊前は「故人を敬って霊前を丁寧にいう言葉」という意味があります。文字から分かるとおり「仏」なのか「霊」なのかの大きな違いがあるのです。
御仏前と御霊前の使い方
仏教では、人が亡くなると「霊」になると考えられています。亡くなってからの四十九日を「中陰」と呼び、四十九日後に閻魔大王の裁きが下ると「仏」になり、極楽浄土へ旅立つのです。
こういった教えを元に、四十九日の法要を迎えるまでは御霊前を使用します。一方、五十日目以降から百日忌法要や三回忌、七回忌などの年忌法要の表書きには、御仏前を記すことが基本です。
浄土真宗では「御霊前」は使わない?
浄土真宗を中心に真宗各派は「人が亡くなると霊になる」という考え方がありません。命を終えると直ちに極楽浄土に往生するという即得往生(そくとくおうじょう)の教えを元にしたとらえ方ですが「霊にならない」ため、御霊前という言葉は一貫して使用せず、最初から御仏前を表書きに使用します。故人はもちろん、ご家庭や地域の習わしなどで御仏前なのか、御霊前なのかが変わることも覚えておきましょう。
御仏前の書き方・包み方
香典袋を例に、御仏前の書き方についてご紹介していきます。
のし袋はどんなものを用意する?
御仏前として使用するのし袋は、黒白の水引を結び切り(あわび結びも可)を用意しましょう。
結び切りは、一度結んでしまうとほどけない結び方です。そのため「繰り返さない」という意味があり、弔事に使用することが一般的です。水引の色は、白黒または双方が銀、双方が白のものをご用意ください。
名前はどう書く?連名にする場合はどうする?
表書きには、水引より上に「御仏前」と書き、水引より下側に氏名を書きます。この時、御仏前の文字よりも少し小さめに名前を書くとバランスが良いためオススメです。
共通の友人と連名で名前を書く場合、年長者の順に右側から書きます。
夫婦で参列する場合、夫の名前を記載するのが一般的です。しかし、夫婦でお付き合いがある方や、妻側の親族に渡す場合などには夫婦連名で書いても問題はありません。
墨はどんな色をチョイスすべき?
「悲しみの涙で墨が薄れる」という意味合いから、薄墨を使用することが基本です。手元に薄墨がない場合は、コンビニやスーパーでも販売されているため用意しましょう。毛筆で書くことが礼儀とされていますが、筆ペンやサインペンを代用しても問題ありません。
新札の使用はOK?
御仏前としてお金を包む場合、新札の使用はNGです。手元に新札しか持ち合わせていない場合であれば、折り目をつけてから包むようにしましょう。
中袋は何を書く?
中袋には、表面に封入した金額を旧漢字で書くことが礼儀です。裏面には、渡す人の住所と名前を記しましょう。
中袋も薄墨を使用して
中袋も表書き同様に薄墨を使用し記述しましょう。こちらも毛筆で書くことが礼儀とされていますが、筆ペンやサインペンを使用しても問題ありません。
中袋の表には封入している金額を明記
中袋の表面に書く「封入した金額」ですが、旧字で書くことが基本です。以下の旧字を参考にしてください。
《漢字》
| 一 → 壱 | 八 → 八 |
| ニ → 弐 | 十 → 拾 |
| 三 → 参 | 百 → 佰 |
| 五 → 伍 | 千 → 仟 |
| 七 → 七 | 万 → 萬 |
| 円 → 園 |
《記述例》
| 3000円 | 金参仟円 |
| 5000円 | 金伍阡円 |
| 10,000円 | 金壱萬円 |
| 30,000円 | 金参萬円 |
| 50,000円 | 金伍萬円 |
| 100,000円 | 金拾萬円 |
| 1,000,000円 | 金佰萬圓 |
h3御仏前として包む金額の相場って?
法要の時期や、故人との付き合いの深さなどの関係性に応じて金額を検討されると良いでしょう。また、出される方の年齢を考慮して用意することもオススメです。一般的には5千円〜1万円が目安とされていますが、3千円でも問題はありません。
御仏前を頂いたらお返しも忘れずに
御仏前を頂いた場合には、お返しを用意することがマナーです。法事や法要に参加していただいたのであれば、当日に引出物としてお渡ししましょう。参加されていない方から御仏前を頂戴した場合には、1カ月間を目処としてお返しを渡すようにしてださい。
御仏前のお返しの目安
御仏前のお返しは、頂戴した金額の3割から半分程度を目安に用意することが一般的です。1万円であれば、3千円から5千円を目安となります。
当日のお返しはどの金額で用意する?
当日にお返しを渡す場合は、2千円から3千円程度の物を一律に用意し、お渡しすることも問題ありません。しかし、当日分だけではお返しが足りないケースが考えられます。その場合は、四十九日法要の後に足りなかった分をお渡しし、本来お返しすべきだった額程度となるようお返しを調整しましょう。
例:当日に1万円をもらったが、当日用意したお返しは3千円のものだった。
→四十九日法要の後に改めて2500円分の品物をお渡しし、合わせて5千円程度になるようにお返しをした。
御仏前は仏前を丁寧に言った言葉
仏前を丁寧に言った言葉が「御仏前」です。似た言葉に「御霊前」がありますが、四十九日を境に使い方が変わるため、ご香典を用意する際には注意が必要です。また、浄土真宗などの真宗では霊ではなく仏になると考えられているため、御霊前の使用はありません。宗派により言葉の使用にも差があることを覚えておきましょう。
香典返しに何を渡したらいいのか悩みますよね。大規模な葬儀の場合は葬儀会社に一任してもいいと思いますが、家族葬など小規模な葬儀の場合は出席者の人数も少ないため、香典にもこだわりたいですよね。そこで、ここでは香典や内祝いにも使える冠婚葬祭向けギフト業者を紹介します。
おこころざし.com

法事や香典返しに特化した専門オンラインショップ。一度に多くの方へのお返しに便利なカタログギフトをはじめ、仏事にふさわしいタオルや食品などを幅広く取り揃えています。
カタログギフトのハーモニック
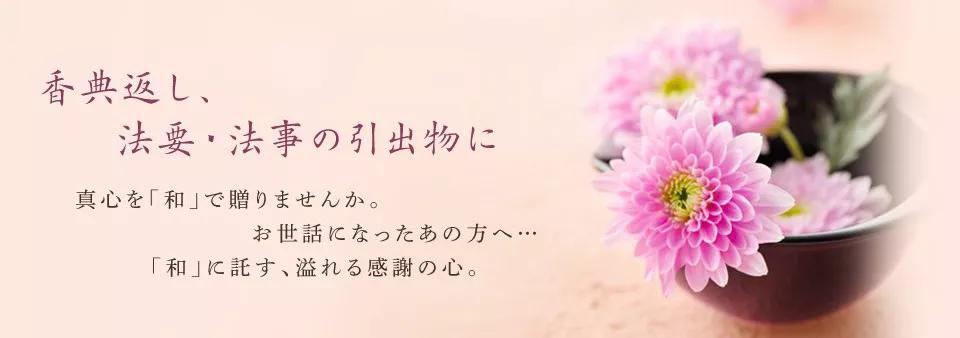
業界トップの品揃えと高品質で、お客様にご満足いただけるカタログギフトを提供しているハーモニック。20種類以上のカタログギフトを、贈り先や用途に合わせて取り揃えています。
また、すべてのカタログギフトは全国送料無料!ラッピングやのし、リボンから挨拶状、手提げ袋まで、すべて無料でご利用いただけます。さらに、ご購入金額の5%を還元するお得なポイントシステムもご用意しています。
シャディギフトモール

贈り物ならば、内祝いから中元、歳暮、おせち、母の日、父の日まで、ギフト専門店シャディの公式オンラインショップがおすすめです。『シャディ株式会社』は1926年創業のギフト専門店で、公式通販サイト「シャディギフトモール」では1万点以上の商品を取り揃えています。
包装やのし紙、紙袋、メッセージカードも無料で用意しており、出産内祝い、結婚内祝い、快気祝い、香典返し、出産祝い、結婚祝い、お中元、お歳暮、おせち、入進学内祝い、手土産、母の日、父の日など、さまざまな用途に対応しています。さらに、カタログギフトの提案や特典のキャンペーンも充実しています。また、新規会員登録で500円クーポンがもらえたり、出産内祝いキャンペーンではベビーグッズ、結婚内祝いキャンペーンでは今治タオルがもらえるなど、お得な企画もあります。
贈り物のコンシェルジュ リンベル

創業以来、1億冊以上の利用実績を誇るカタログギフトのトップブランドです。年間950万件のギフト受け取り実績があり、受け取った方の94%から満足の評価を得ています。
業界トップの品揃えと、時代に合った高品質な商品ラインナップを提供。結婚引出物や結婚・出産の内祝い、香典返し、お中元・お歳暮など、さまざまな冠婚葬祭や贈り物に最適なカタログギフトをご用意しています。贈られた方が自分の好みに合わせて商品を選べるのが特徴です。贈答のプロが厳選したアイテムや、食品、洋菓子、日用品、産地商品など、幅広い品揃えも魅力的です。
1)KASHIYAMA(カシマヤ)
KASHIMAYA(カシマヤ)は、高品質ながら手頃な価格で、自社工場で最新技術を駆使したオーダースーツを最短1週間での納期を実現しました。また、2021年3月にスタートした新ライン「KASHIYAMA EASY」は、商品の品質や自動採寸の精度、納期、着こなしの汎用性に自信を持っています。これにより、より多くの人々が快適なオーダースーツを手に入れることができます。
KASHIMAYA(カシマヤ)のオススメデザイン
KASHIMAYA(カシマヤ)のセットアップスーツ/オーダーメイドスーツ

「身長・体重・年齢・体型」を入力するだけで、あなたにぴったりのサイズを提案するオンライン完結型のオーダーメイドシステム。採寸結果に基づいて1cm単位で調整が可能であり、日本人の90%以上の体型に対応する高い採寸精度を誇ります。
さらに、オーダーなのに最短1週間での納期を実現。超撥水性やウォッシャブル、超軽量、ストレッチなど、約150種類の素材やカラーを用意しています。オーダーメイドならではのデザインバリエーションもあり、ジャケットは2型、パンツは4型から選ぶことができます。これらの特長が、より快適なオーダーメイドスーツを実現しています。
《参考》KASHIMAYA(カシマヤ)
2)ORIHICA(オリヒカ)
ORIHICA(オリヒカ)は、メンズ&レディースのビジネスカジュアルブランドです。現代の多様な働き方に合わせて、ビジネスからカジュアルまで幅広い商品を取り揃えています。
ブランドのコンセプトは「新しいライフスタイルの鍵」。次世代のライフスタイルを切り拓く存在として、カテゴリーにとらわれずにアイテムを自由に編集する楽しさを提案しています。ORIHICAは、個々のスタイルやニーズに合わせたオシャレな選択肢を提供します。
ORIHICA(オリヒカ)のオススメデザイン
ナノブラック フォーマルスーツ 通年

社会人にとって必須のブラックフォーマル(喪服・礼服)は、特殊な加工を施した生地を使用しています。羊毛表面のスケールを取り除き、ナノレベルの染色剤を使って繊維の奥深くまで濃い黒を浸透させています。一般的なブラックスーツよりも上品で深みのある黒を実現しました。特に格式高い結婚式や披露宴では、濃い黒の方がよりフォーマルな印象を与えます。さらに、カーボン繊維を混紡することで、埃がつきにくくなっています。
このブラックフォーマルには、光沢感のあるピアノブラック釦が使用されています。光沢感がよりフォーマルな雰囲気を演出します。背中の裏地がなく背抜き仕様になっているため、オールシーズン着用可能です。さらに、ウエストアジャスターがあり、体型の変化にも対応しています。これにより、長く着用することができる魅力的なスーツです。着用頻度の低いスーツであるからこそ、これらの仕様は嬉しいものです。
《参考》ORIHICA(オリヒカ)
喪服・礼服・数珠をレンタルするという選択
喪服や礼服はいざという時に必要ですが、それ以外の時にはクローゼットの奥に眠っていることが多いですよね。また、必要になるのはいつも突然で、クリーニングに出す暇がない、なんてこともありませんか。
急な状況でも綺麗な喪服・礼服を準備するならレンタルという選択肢があります。
例えば「Cariru BLACK FORMAL」はドレスレンタルCariruが培った信頼と実績を、ブラックフォーマル特化させたフォーマル専門のレンタルサイト。質にこだわり、時代に合った高いデザイン性と確かなブランド力を提供しつつ、初めてブラックフォーマルを利用する方や、サイズやデザインに合わなくなった方、上質を求める方に向けて、Cariruが品質の高い選択肢を提供しています。
また、すべての商品は弔事のマナーに厳密に則って厳選されているため、突然の訃報に直面しても、通夜や葬式などへ参列できます。必要な時に必要なものがすべて揃う、デザイン・質・マナーを疎かにできない大人のためのブラックフォーマルレンタルがCariru BLACK FORMALです。