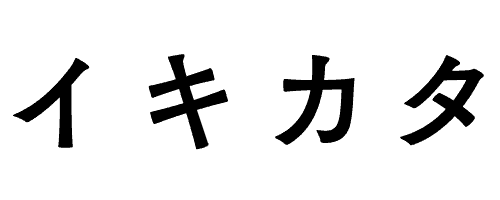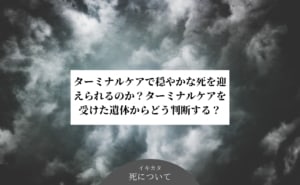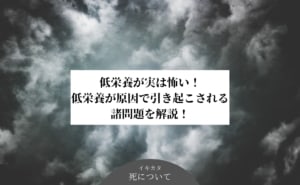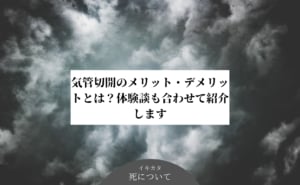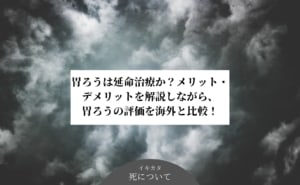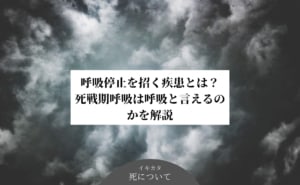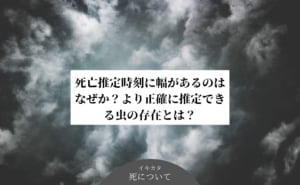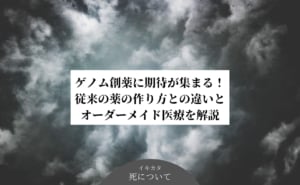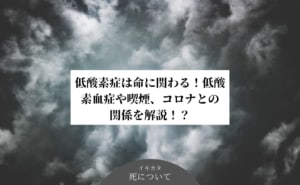本ページはプロモーションが含まれています。
心肺が停止した時の脳のダメージは?!意識はあるのか?
心肺停止後に脳はどんなダメージを受ける?
心肺が停止すると、脳の活動も急に終わるとされてきました。言い換えると心臓が止まれば、「死んだ」とみなされることが多いですが、実際は「死んだ」とは断定できません。さらに救命処置が早ければ早いほど、1か月後に社会復帰できる可能性が高くなります。心肺が停止したとき、脳の活動はどのように変化するのでしょうか?意識は心肺停止と同時になくなるのでしょうか?
心肺停止してから意識が戻らない理由
心肺停止とは心臓と肺の動きが止まることですが、心臓の機能が止まると血液は全身を流れなくなります。脳へ流れる血液も止まり、脳細胞が死んでいくわけです。脳の大半を占める大脳。感情や認知に関係する大脳の機能が停止してしまうと、意識は戻らなくなります。
心肺が停止してから迫られる決断
心肺停止後に医師から「意識が戻る可能性は低い」と宣告されたとき、家族は延命するか否かの決断を迫られます。
延命治療とは命を引きとどめ続ける治療
延命治療とは、「命を引き止め続ける治療」です。脳卒中などで突然、心肺停止した場合、医師は「命を取り止める治療」、救命処置をします。しかし心肺停止してから救命処置までに時間がかかっているケースが大半なため、意識が戻ることはほとんどありません。
とはいえ、医師の「意識は戻らないだろう」という宣告は、家族にとっては受け入れ難いもの。「とにかく命は助けてほしい」と懇願されることもあるそうです。救命処置として人工呼吸器をつけると、そのまま延命治療が続くことが多いと言われています。延命治療を始めた場合、途中で治療を止めるかどうかの決断をまた迫られるかもしれません。
心肺停止から脳死にいたるまでの時間*₂
心肺停止後3~5分後で脳に酸素がいかなくなり、脳死にいたると言われています。脳は心肺停止後1分で機能停止。4分で脳に蓄えられていた酸素を使い果たし、さらに心肺停止後15分で脳の損傷が始まるとされています。心肺停止後15分以降で、たとえ蘇生しても麻痺などの後遺症が残るそうです。
心肺停止後でも助かる確率*₁
心肺停止後、血流がストップして各臓器は機能を停止します。しかし、心肺停止が「死」と診断されないのは、わずかとはいえ蘇生して意識を取り戻す可能性があるため。ここでは心肺が停止した後に助かる確率をみていきます。
救命率と蘇生率の違い
「救命率」と「蘇生率」は意味が違います。救命率とは、心肺が停止してしまった人の心拍が戻りまた意識も戻る率のこと。社会復帰できることを意味します。一方、蘇生率とは心拍が戻っただけの率。意識は戻っていない状態です。
心肺停止後の経過時間と脳の損傷
心肺停止すると脳へ血液が流れなくなるために、脳はダメージを受けます。脳が受けるダメージは時間の経過とともに深刻化。
心肺停止後1分以内で救命処置がなされれば、救命率は95%です。3分以内なら75%と、対処が早ければ早いほど脳が受けるダメージも少ないと言われています。5分後になると25%。8分以降になるとほとんど救命の可能性はないそうです。
心肺蘇生と社会復帰
病院外で心肺停止した場合、1か月後に社会復帰できる可能性は9%未満。しかし心停止後に心肺蘇生をすると、1か月後に社会復帰できる可能性は16%強にまで高くなることが報告されています*₂。
もし人が突然に倒れて正常な呼吸がみられない場合は、速やかに119番通報をしましょう。加えて救急隊が到着するまでに心肺蘇生を試みます。心臓マッサージを30回行ってから人工呼吸を2回。これを繰り返し、近くにAEDがあれば迷わず使いましょう。
心肺停止後5分間の意識
最近の研究では、心肺停止後にいわゆる「死」の宣告を受けた後にも、意識があるのではないかという報告があります。
蘇生患者からの聞き取り:心肺停止後の意識*₃
2014年10月英国サウサンプトン大学の研究によれば、心停止から蘇生した330人のうち101人に聞き取り調査。39%の患者が心臓が再び動き出す前に、意識を自覚していたそうです。
生命維持装置を外した患者:脳波の観測*₄
2017年3月カナダのウエスタンオンタリオ大学の研究があります。生命維持装置を外して心臓と血流が停止した後の10分間に、脳波を観測できた患者が1人いました。この患者から計測できた脳波は深い睡眠時にみられるときのものでした。
蘇生患者の証言:医療スタッフの会話*₃
米ニューヨーク大学が米と欧州で調査を実施。2017年、心臓発作を起こして「死」を宣告された後に蘇生した患者330人を対象としたもので、実際に聴き取りをした101人の患者の中には、「死」を宣告された後に起こったことを証言した者もいました。
周囲でどんな会話がされたか、自身に何が起こったか、証言した内容と周囲にいた医療スタッフの証言は一致したそうです。
最期まで残る聴力
「耳は最期まで聞こえる」ことは以前から言われています。実際に患者が危険な状態のとき、医療従事者は家族に対して患者に呼びかけることを促します。
2007年アメリカの『TIME』誌によると、蘇生した患者の4~18%が「自分の耳元で名前を呼びかける声が聞こえた」と証言したそうです。
まとめ
道を歩いていて突然、人が倒れたとき、救急車到着まで心肺蘇生をするかしないかで1か月後の社会復帰できる可能性が変わってくるそうです。冷静に勇気をもった行動が必要とされています。
また心肺停止後の救命処置で心拍が戻っても意識が戻らない場合、家族に重い決断が迫られます。日頃、家族間でどこまでの治療を望むか、つまり延命治療を望むかどうかを話し合っているかどうか。ここを話し合っていない家族が多いことを医師は嘆きます。「死は先のこと」とする人が多いですが、「死はいつ訪れるかわからない」こととして、延命治療を望むか望まないか、家族間で話し合っておくことは大事でしょう。
さらに、心肺停止後でも意識がある可能性があるという報告があります。本人は目に見えた意思表示ができない状況ですが、実は話し声などは聞こえているのかもしれません。自分自身が死に瀕した時のために、死というものをきちんと考えておくことが必要なのです。
*1痛みの話Q&Aー八王子整形外科
http://www.hachiouji-seikei.com/search/15.html
*2死の淵に立つ心肺停止、心肺と脳の蘇生で社会復帰率向上を支援する世界初の装置
https://ins.minkabu.jp/articles/48
*3心肺停止後、5分は意識がある!?最新の脳神経学で分かった「死」ーNewsweekjapan
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/03/5-40.php
*4死の瞬間も声は聞こえているのか 研究データから見る真偽ーライブドアニュース