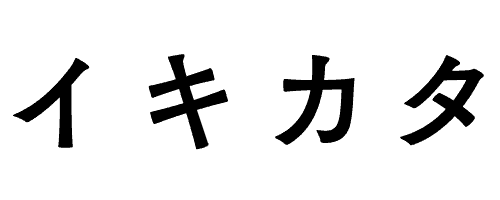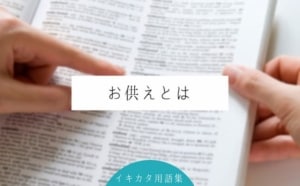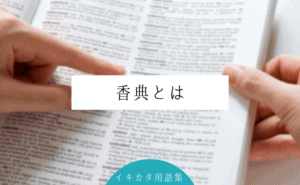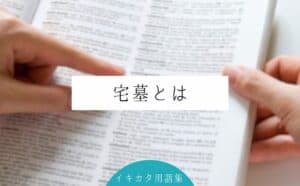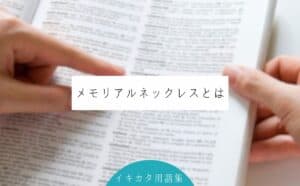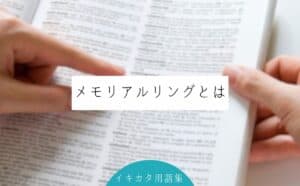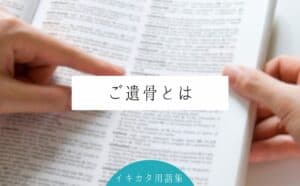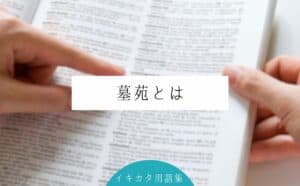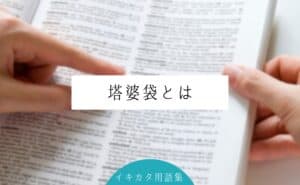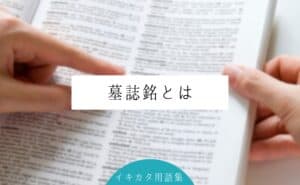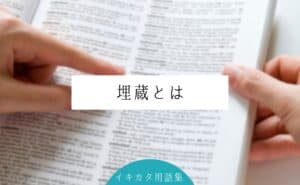本ページはプロモーションが含まれています。
百箇日とは?お布施・服装・香典・お供えは?準備・当日の流れ・百箇日の別名も紹介
百箇日とは故人の没後100日目に迎える法要
百箇日とは、故人の没後100日目のことを指し、この日に営む法要を百箇日法要といいます。
このため、百箇日法要は忌明け後に営む最初の法要であり、とても大切なものといわれています。
しかし、近年では、忌明けとなる49日法要のあとは一周忌法要を営むことが多く、百箇日法要に馴染みがないという場合も少なくありません。
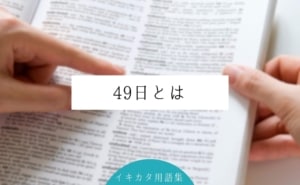
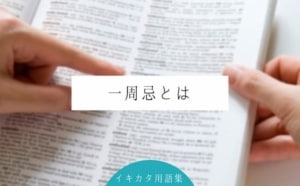
また、宗派や菩提寺の考え方、地域性により百箇日法要を営まないケースもあります。
別名「卒哭忌(そっこくき)」
百箇日法要には「卒哭忌」という別名があります。
「卒」は「卒業」の意味、「哭」は「声を出しながら涙を流す」状態のことです。つまり、百箇日法要は大切な人を失った悲しみや苦しみに別れを告げ、前に進むための儀式ともいえるでしょう。
百箇日にあわせて「偲ぶ会」を開催することも
百箇日法要に合わせて故人を追悼する「偲ぶ会(お別れ会)」を開催することもあります。
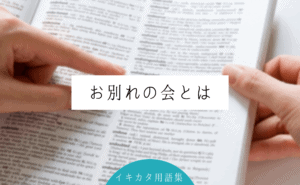
百箇日法要の遺族側の準備
百箇日法要は、親族のみで営むことが一般的です。しかし、百箇日法要を重視する地域では、故人の友人など親族以外の人を招くケースもあります。故人や参列者に失礼のないよう、準備を進めておくことが大切です。
法要の日取りを決める
百箇日法要は、亡くなった日から数えて100日目に営むことが基本です。
しかし、100日目が必ずしも休日とは言い切れません。100日目が平日に当たる場合は仕事などで参列しづらいことを考慮し、前倒しした休日に計画すると良いでしょう。また、100日目を過ぎてからの日程で計画することはNGです。
なお、日取りを決める際は、百箇日法要をお世話になる寺院・僧侶の予定が問題ないかを必ず確認するようにしましょう。
法要を営む場所を決める
百箇日法要は、自宅で営むことが一般的ですが、葬儀会場などでも可能です。参列者の人数、交通の便や予算などに合わせて法要を営む場所を決めると良いでしょう。
参列者に知らせる
百箇日法要の日時や場所が決まれば、参列者にお知らせしましょう。
連絡する方法は、親族や親しい人であれば電話連絡でも問題ありません。法要の規模が大きくなる場合は、案内状の送付を検討すると良いですね。
なお、法要後に偲ぶ会を開催する場合は、あわせてお知らせするようにしましょう。
お斎の食事手配
百箇日法要の後は「お斎(おとき:法要後に参列者に振る舞う食事会)」を開催することが多いです。
お斎を検討し、開催する場合は食事の手配を進めましょう。自宅を会場とする場合は仕出し弁当などを注文するケースが多いですが、料亭やホテルなどで開催することもあります。
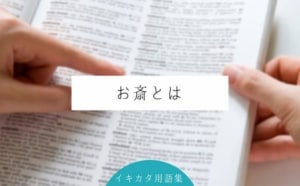
お布施の用意
百箇日法要でのお布施は3万円〜5万円が相場です。
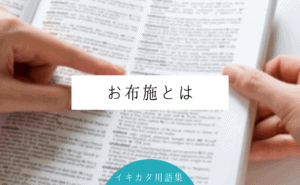
場合によっては、お車料や御膳料をお渡しすることもあります。これらが必要になる場合には、お布施とは合算せず、別々に準備しておきましょう。
目安
お車料:5,000円程度
御膳料:5,000円〜1万円程度
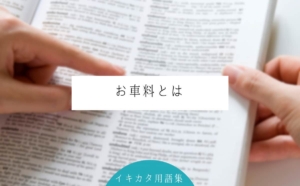
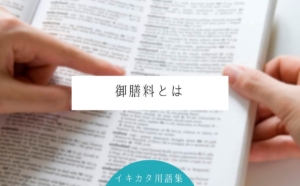
お供物・供花の手配
お供物は、線香やお茶、果物、お菓子など参列者で分けられるもの、また、故人が好きだったものを選ぶと良いでしょう。
ただし、肉や魚などは、殺生をイメージさせてしまうため、仏教の視点からすると適している品物だとはいえません。これらが故人の好みだったとしても、供えないようにしましょう。
供花は、白を基調に故人が好んだ花を選ぶと良いでしょう。薔薇などトゲがある花は、トゲをとるようにしましょう。
百箇日法要の当日の流れ
百箇日法要の当日の流れは以下の通りです。
1)施主の挨拶
2)僧侶の読経
3)参列者の焼香
4)僧侶の法話
5)施主の挨拶
6)会食(お斎)
百箇日法要の後、納骨をする地域もあります。
香典返しに何を渡したらいいのか悩みますよね。大規模な葬儀の場合は葬儀会社に一任してもいいと思いますが、家族葬など小規模な葬儀の場合は出席者の人数も少ないため、香典にもこだわりたいですよね。そこで、ここでは香典や内祝いにも使える冠婚葬祭向けギフト業者を紹介します。
おこころざし.com

法事や香典返しに特化した専門オンラインショップ。一度に多くの方へのお返しに便利なカタログギフトをはじめ、仏事にふさわしいタオルや食品などを幅広く取り揃えています。
カタログギフトのハーモニック
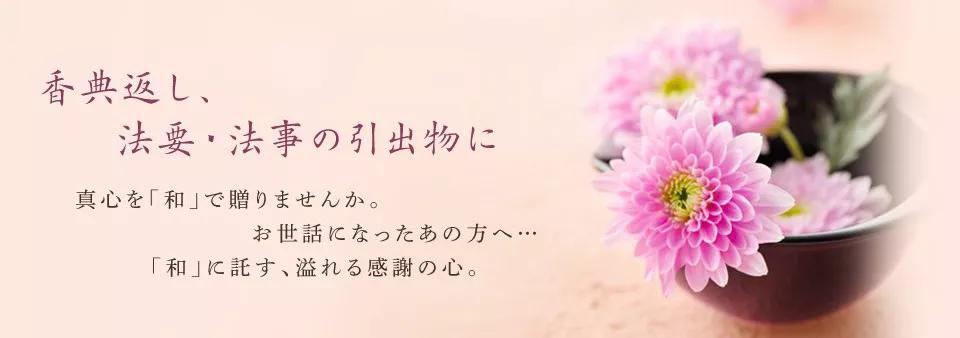
業界トップの品揃えと高品質で、お客様にご満足いただけるカタログギフトを提供しているハーモニック。20種類以上のカタログギフトを、贈り先や用途に合わせて取り揃えています。
また、すべてのカタログギフトは全国送料無料!ラッピングやのし、リボンから挨拶状、手提げ袋まで、すべて無料でご利用いただけます。さらに、ご購入金額の5%を還元するお得なポイントシステムもご用意しています。
シャディギフトモール

贈り物ならば、内祝いから中元、歳暮、おせち、母の日、父の日まで、ギフト専門店シャディの公式オンラインショップがおすすめです。『シャディ株式会社』は1926年創業のギフト専門店で、公式通販サイト「シャディギフトモール」では1万点以上の商品を取り揃えています。
包装やのし紙、紙袋、メッセージカードも無料で用意しており、出産内祝い、結婚内祝い、快気祝い、香典返し、出産祝い、結婚祝い、お中元、お歳暮、おせち、入進学内祝い、手土産、母の日、父の日など、さまざまな用途に対応しています。さらに、カタログギフトの提案や特典のキャンペーンも充実しています。また、新規会員登録で500円クーポンがもらえたり、出産内祝いキャンペーンではベビーグッズ、結婚内祝いキャンペーンでは今治タオルがもらえるなど、お得な企画もあります。
贈り物のコンシェルジュ リンベル

創業以来、1億冊以上の利用実績を誇るカタログギフトのトップブランドです。年間950万件のギフト受け取り実績があり、受け取った方の94%から満足の評価を得ています。
業界トップの品揃えと、時代に合った高品質な商品ラインナップを提供。結婚引出物や結婚・出産の内祝い、香典返し、お中元・お歳暮など、さまざまな冠婚葬祭や贈り物に最適なカタログギフトをご用意しています。贈られた方が自分の好みに合わせて商品を選べるのが特徴です。贈答のプロが厳選したアイテムや、食品、洋菓子、日用品、産地商品など、幅広い品揃えも魅力的です。
百箇日に対してよくある質問
まとめ:百箇日とは故人が他界してから100日目のことで、その時に営む法要のこと
百箇日は、故人の没後100日目を指し、そのときに営む法要を意味することもあります。多くは、家族や親族だけで営みますが、故人の友人なども招待し、盛大に営むこともあります。
また、100日目が平日に当たる場合は、前倒しした休日に予定することがマナーです。
百箇日は「卒哭忌(そっこくき)」と呼ばれているとおり、大切な家族の旅立ちに悲しみを寄せつつ、深く重い悲しみから離れるための節目と捉えると良いでしょう。